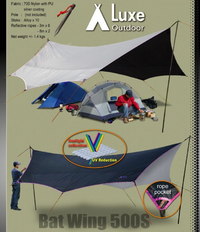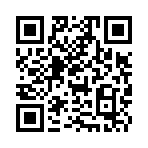2006年11月19日
LEDは本当に明るいのか?
いつの間にか増えてしまったもの・・・それは・・・

各種ランプ類です。
半年から1年もすると技術革新で新型が出るわ、お値段も手ごろなもんで、いつの間にか増え続けています。
こういうエレクトリック関係の物は、ナイフやバーナーと違い
これさえあれば!
という、謂わば定番品に出会えませんね。
ということは永久に新規購入し続ける羽目に陥る商品です。(^^ゞ
この所、省電力がらみでLEDについて調べるうちに表題の疑問にぶち当たりました。
ちまたでは今、LED真っ盛りです。アウトドア用品では、ハンディライトやヘッドランプはかなりのシェアがLEDになっています。最近では、ランタン類にもLEDの商品が増えてきています。
僕は長らくキャンドルランタンを愛用していますが、ホヤの固定性が落ちてきたので買い換えようかと思っています。今度はコンパクトでも明るいランタンが欲しいんですが、性能を比較しようとした所、ワット表示だったり、ルクスだったり、ルーメンだったり、キャンドルパワーなんて単位も出てきて簡単には比較できないんですよね。(--〆)
そこへ来て今回の疑問です
LEDは本当に明るいのか?
各種ランプ類です。
半年から1年もすると技術革新で新型が出るわ、お値段も手ごろなもんで、いつの間にか増え続けています。

こういうエレクトリック関係の物は、ナイフやバーナーと違い
これさえあれば!
という、謂わば定番品に出会えませんね。
ということは永久に新規購入し続ける羽目に陥る商品です。(^^ゞ
この所、省電力がらみでLEDについて調べるうちに表題の疑問にぶち当たりました。
ちまたでは今、LED真っ盛りです。アウトドア用品では、ハンディライトやヘッドランプはかなりのシェアがLEDになっています。最近では、ランタン類にもLEDの商品が増えてきています。
僕は長らくキャンドルランタンを愛用していますが、ホヤの固定性が落ちてきたので買い換えようかと思っています。今度はコンパクトでも明るいランタンが欲しいんですが、性能を比較しようとした所、ワット表示だったり、ルクスだったり、ルーメンだったり、キャンドルパワーなんて単位も出てきて簡単には比較できないんですよね。(--〆)
そこへ来て今回の疑問です
LEDは本当に明るいのか?
調べれば調べるほど
嘘じゃないけど、正しくもない。
という結論に至ります。
LEDの商品コピー(表現は微妙に異なります)をまともに信じると、
1、熱が出ない。(エネルギーロスが少ない)
2、高効率で省電力、さらに明るい(白い光)。
3、寿命が長い。(さすがに最近は”半永久的”なんて言わなくなりつつあります。)
あたりが大きなウリですね。
ところが調べてみると、3番目の寿命が長い以外は意外にそうでもないようです。
前提条件があるんですよ。
「この範囲でなら」とか「~と比べて」
という、特定条件なら全て嘘じゃないようです。しかしながら、LEDは照明用光源として捉えた場合、もっと根源的な問題があります。それは
現時点では、単体では5W(ワット)クラスまでしかありません。しかもかなり発熱します。
つまり、単体では総出力が桁違いに小さいんです。
あかり(光)の強さを表す単位は色々有ってややこしいです。ルクス(照度)で統一してくれると一番わかりやすいと思うんですが、そうもいかないようです。
理由は、光源の特性によってその性能を表現するのに適した規格を採用しているためです。
例えば、LEDは指向性が強い光源ですが、レーザー光などはその極端な例です。何処まで行っても殆んど広がりません(拡散しない)から、照らされた部分の明るさ(照度)をルクスで表現しても意味がありません。エネルギーとしての強さを要求されるのでW(ワット)やJ(ジュール)で表現されます。
知ったような事を書いてますが、この間かなり勉強したんです。が、未だに良くわかってないことが多いです。(^^ゞ
次のサイトにとてもわかりやすくまとめて下さっています。→光と光の記録
さて肝心の明るさの比較をするための規格(単位)ですが、悩みに悩んだ挙句、どうやらルーメン(光束)で比較するのが良さそうです。
ルーメン(光束)というのは馴染みの薄い言葉ですが、意味する所は
単位空間に放射される光の量を表す単位です。
光源から放射される光を糸のように見立てたもので、光の糸の密度が濃ければ明るい光源ということになります。
カンデラ(光度)、ルクス(照度)、ルーメン(光束)という関係を言葉で表現するとややこしいので、先程のHPに乗っているわかり易い図を載せておきます。

ここでちょっと脱線しますが、皆さん電気器具の”消費電力~W(ワット)”っていうのを良くご存知だと思います。これって照明用器具でも同じだって事知ってました?
つまり何が言いたいかって言うと、照明用電球の~Wって言うのは”消費電力”であって、”出力=明るさ”を表していないんです。僕は何の考えも無く、明るさ=W(ワット)数と勘違いしてました。”効率”が関与しますから、言われてみれば当たり前のことなんですよね。(^^ゞ
例えば白熱電球の場合、使用する電気エネルギの90%近くが熱になり残りの10%程度が光になります。従って、60Wの白熱電球が放出する光エネルギーは6W程度となります。そう思うと、6Wって意外に明るいですよね。
白熱電球よりも高効率を謳うハロゲンバルブでは、フィラメント温度が同じであれば寿命を2倍にでき、同一寿命であれば効率が約15%高くなります。ちなみに、ハロゲンランプは、寿命末期に至るまで光束の低下がほとんど無いそうです。比較的安価で輝度も高いため広い応用範囲に使用されています。
そんなこんなで気になるのが”変換効率”です。調べてみると

いや~、正直
がっかり(--〆)です。
”LEDは発熱しなくて高効率”なんて言ってますが、それは”白熱電球に比べれば”であって、蛍光灯のほうが2倍程高いんです。
確かに新しいデバイスですから日々、発光効率は改善されています。しかし、それは他の発光形式の電球でも同じことです。放電灯が総じて高効率で高出力ですが、フィラメントやエミッターの寿命という弱点を持っていました。ところが最近になって無電極放電灯が商品化されました。画期的な長寿命と省電力(高効率)を実現しています。HIDランプに至っても高電圧発生回路がネックでしたが、現在はここまで小型化されています。これらは確かにまだまだ高額ですが、これらの製品のコストダウンが先か、それともLEDの効率改善・大容量化が先かは予断を許しません。発光特性や器具としての特性が異なりますから、競合することなく住み分けられるので要らぬ心配することは無いですかね。(^^ゞ
この辺のネタは、調べれば調べるほど出てくるんですが、脱線はこのくらいで
ようやく長い前フリも終わり、核心のLEDと他のデバイスとの明るさの比較です。
発光体の大きさや、発光特性そのものが違ったり、中には明確な特性表記がされていない物を、なかば強引に比較しますから目安程度にしかならない事をことわって置きます。
光源の明るさを示す単位として最近はルーメン(全光束)がよく用いられますが、白熱電球の場合は40型(36W)で470ルーメン、蛍光ランプの場合では20型(20W)で1150ルーメンぐらいです。これらはデータシートとして公開されています。ランプの規格が同じなら、メーカーが違っても殆んど同じ値です。JIS規格か何かで決まっているのかもしれません。ちなみに手元にある蛍光灯付き懐中電灯は4Wの蛍光管が付いています。昼光色で95ルーメン、白色で110ルーメンあります。6Wの蛍光管だと210~240ルーメンです。
この蛍光灯付き懐中電灯は豆球も付いていますが、残念ながら豆球のデータは公開されていません。
白色LEDの場合は1Wがおよそ38ルーメン、3Wで70ルーメン、5Wで130~160ルーメンぐらいです。それ以下の消費電力のLEDはこちらの表に出ているのを参考にします。
基本的に今はランタンとしての照明性能を探求していますので指向特性の狭いものは除外し、拡散性の強いもので比較してみます。
どんぶり勘定で2~5ルーメン弱というところでしょうか?
【ルーメンとカンデラとの違い】
・光束(ルーメン:lm)を光度(カンデラ:cd)に換算するのは実際には難しいです。カンデラは光を1点の点光源とみなしその点光源から発する光の強さをいうのに対し、ルーメンは360度全立体方向(立体角、ステラジアン:sr)に放射する全体の光の量をあらわす違いがあります。立体角1ステラジアンだけの光の強さを見た場合はルーメン値=カンデラ値となります。cd=lm/sr(カンデラ=ルーメン÷ステラジアン)
指向特性の角度は定格光度の半分50%以上の光度の範囲を表します。(半値角)
・指向特性70度・・光度/光束(カンデラ/ルーメン)cd/lm=0.6、(例)4.8ルーメン=4.8×0.6cd=2.88cd=2880mcd です。
・指向特性30度・・光度/光束(カンデラ/ルーメン)cd/lm=2.0、(例)4.8ルーメン=4.8×2.0cd=9.60cd=9600mcd です。
(光度/光束の定数は各製品によって異なりますので注意してください。) だそうです。(^^ゞ
蛇足ですが、自動車用のHIDの場合、35Wタイプで3000~3200ルーメンです。55Wのハロゲンバルブで1550ルーメン程度だそうです。ハンディーHIDライト(21W)で1000ルーメン・10万カンデラです。 まさに桁違いですね。
まさに桁違いですね。
ハイテクばかりではなく、ローテク=”蝋燭(ろうそく)”も見てみましょう。
そもそも光の明るさを最初に定義する際に基本となったのはどうも”ろうそく”の明るさのようです。candle powerと呼んだそうで、日本に入った際に”燭(しょく)”と訳されました。現在の光の単位になるカンデラ(candela = cd)は燭とほとんど同じ光度を持った明るさで、燭をもとにして正確なカンデラが制定されました。1燭は、1.0067cd(カンデラ)に相当し、今のカンデラが単位として採用されるまでイギリスや日本などで用いられました。日本では1958年(昭和33年)12月31日に「燭」の使用が廃止されたそうです。この辺の経緯は色んなサイトに記述されているので詳しくはそちらを検索してみてください。ですから・・・コールマンさん、ゲニオールさん、ペトロマックスさん
100キャンドルパワーなんて言い方止めて下さい。!
ま、それは置いといて実際の蝋燭(ろうそく)の明かりですが先程紹介した光と光の記録さんに実測したデータが出ています。それによると1カンデラの明かりを出す蝋燭(ろうそく)は(換算値で)炎の体積が337.5立方ミリメートル程度だそうです。はっきり言って想像つきません。
幅10mm、高さ3.3mm程度の炎の大きさの蝋燭ですね。キャンドルランタンはどの程度なんでしょう?誕生日ケーキにともす蝋燭程度でしょうかねえ?先の条件の炎の蝋燭なら1カンデラ、1ルクス、1ルーメンということになります。
さて、マントルを使う燃焼系ランタンはどうでしょう?最近多い表記は~Wと表現しています。W(ワット)ってもともとは仕事率を表す単位です。調べてみると・・・”放射束 (radiant flux)”という概念で表記するようです。
「放射束は、単位時間あたりの放射エネルギーです。これは時間あたりのエネルギーですから、単位は J s-1 ですが、ジュールはワット秒なので、それを代入すると、単位は単にワット(W)になります。ある光源があった場合、そこから単位時間あたりに放射されるエネルギーを表したいような場合には、この放射束を使うことになります。」
なんて書いてあります。光束(ルーメン)とどう違うんでしょう?
”光”は電磁波です。しかし、電磁波が全て光ではありません。人間の可視領域の電磁波だけを”光”と呼びます。人の目に見える電磁波に限った場合、放射束は光束と呼ばれます。これは人間の目の感覚を考慮しているために心理物理量と呼ばれます。したがって、光束は仕事率ではないためにW(ワット)表示されないのです。
このように人間を基準とした測定するための”測光量”とエネルギー放射としての”放射量”を表記する二つの単位系が使われているんです。(そんなことは先に言ってくれよ~ )
)
主な測光量と対応する放射量
主な測光量 単位 主な放射量 単位
光束(Luminous Flux) lm(ルーメン) ・・・・・・・放射束(Radiant Flux) W
光度(Luminous Intensity) cd(カンデラ) ・・放射強度(Radiant Intensity) W/sr
輝度(Luminance) cd/m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・放射輝度(Radiance) W/sr/m2
照度(Illuminance) lx(ルクス)・・・・・・・・・・・・・放射照度(Irradiance) W/m2
厄介なことに僕には簡単には変換できません。1979年:第16回 国際度量衡総会で変換式が決議されたようですが僕にはちんぷんかんぷんです。
電気製品ならともかく、放射量を示すW(ワット)で燃焼系照明器具の性能表示をすることには疑問を感じます。極端な例ですが100Wの能力を持つマントルランタンがあったとします。そのランタンが99%赤外線を放射し、1%光を出した場合でもそのランタンは100Wの能力を持つことになります。これじゃ明るさの比較なんて出来たもんじゃありません。
具体的に見てみましょう。Coleman(コールマン)ノーススター2000ランタンの場合、カタログによると明るさ:約360CP/230W相当となっています・・・相当・・・相当とな?対白熱電球比較でしょうか?ちょっと合わないんですよね
先ず360キャンドルパワーというんですから、光度は約362cd(カンデラ)です。つまり362ルーメンに相当します。白熱電球40型(消費電流36W)で470ルーメンですから、比較するとかなり暗いことになります。輝度が高いので眩しいですが、光量自体は少ないようです。白熱電球の発光効率は10%ですからどんな電球と比較すると230W相当なんて言えるんでしょうね?200Wのシリカ球なら3200ルーメン、自動車の35WのHIDなみの全光束があります。
嘘つき?
まさかね、天下のコールマンがウソなんてつかないですよね。(;一_一)
きっと何か230Wに相当するものがあるんでしょう。照明器具の歴史の中で当初ガス灯(ランプ)が主流でしたが電球の登場と共に廃れて行ったそうです。しかし、マントル発光が発明されて実用になった時再びガス灯が盛り返した時期があったそうです。その当時の電球はまだ発光効率が低かったんですね。きっとその電球と比較してるんだと・・・信じたい。
この一週間、殆んどこれにかかりきりで調べていました。LEDが本当に明るいかどうかを調べるつもりだったんですが、結果は期待外れでした。
5Wなどという特別容量が大きいものは別ですが、通常の超高輝度レベルのLEDが省電力で持ちがいいのは当たり前です。絶対エネルギー量が少ないんです。つまり光量が少ないですから長くも持ちます。それが証拠に3Wクラス以上の製品は一様に大容量の電池を必要とします。
発光効率は蛍光灯の半分~半分強、改善しつつあります。メリットも多く有ります。確かに寿命が長いです。割れることもありませんし、物理的特性もいいです。器具としてもコンパクトになります。指向性の強さもハンディライトとしたら利点になります。蛍光灯などの水銀灯のように温度低下によって発光効率が下がることもありません。
この一週間で得た成果が2つあります。一つは
蛍光灯の素晴らしさです。
物理的特性は劣りますが、発光効率、容量、コストパフォーマンスはずば抜けています。決して大飯喰らいで効率が悪いなんて事はありません。発光量が大きいですから消費が激しく見えるだけです。
2つ目は
これ程光の単位系が、混沌としているとは思いませんでした。
これ程身近にありながら、これ程理解しがたい難解な状態にあるとは思いも因りませんでした。
照明器具の世界に限っては、あまりに生産者側の身勝手が過ぎると思います。消費者に正しい比較が出来るように、きちんと単位系を整えるべきです。
強い行政指導くらい出来ませんかねえ。(--〆)
(あ~疲れた )
)
嘘じゃないけど、正しくもない。
という結論に至ります。
LEDの商品コピー(表現は微妙に異なります)をまともに信じると、
1、熱が出ない。(エネルギーロスが少ない)
2、高効率で省電力、さらに明るい(白い光)。
3、寿命が長い。(さすがに最近は”半永久的”なんて言わなくなりつつあります。)
あたりが大きなウリですね。
ところが調べてみると、3番目の寿命が長い以外は意外にそうでもないようです。
前提条件があるんですよ。
「この範囲でなら」とか「~と比べて」
という、特定条件なら全て嘘じゃないようです。しかしながら、LEDは照明用光源として捉えた場合、もっと根源的な問題があります。それは
現時点では、単体では5W(ワット)クラスまでしかありません。しかもかなり発熱します。
つまり、単体では総出力が桁違いに小さいんです。
あかり(光)の強さを表す単位は色々有ってややこしいです。ルクス(照度)で統一してくれると一番わかりやすいと思うんですが、そうもいかないようです。
理由は、光源の特性によってその性能を表現するのに適した規格を採用しているためです。
例えば、LEDは指向性が強い光源ですが、レーザー光などはその極端な例です。何処まで行っても殆んど広がりません(拡散しない)から、照らされた部分の明るさ(照度)をルクスで表現しても意味がありません。エネルギーとしての強さを要求されるのでW(ワット)やJ(ジュール)で表現されます。
知ったような事を書いてますが、この間かなり勉強したんです。が、未だに良くわかってないことが多いです。(^^ゞ
次のサイトにとてもわかりやすくまとめて下さっています。→光と光の記録
さて肝心の明るさの比較をするための規格(単位)ですが、悩みに悩んだ挙句、どうやらルーメン(光束)で比較するのが良さそうです。
ルーメン(光束)というのは馴染みの薄い言葉ですが、意味する所は
単位空間に放射される光の量を表す単位です。
光源から放射される光を糸のように見立てたもので、光の糸の密度が濃ければ明るい光源ということになります。
カンデラ(光度)、ルクス(照度)、ルーメン(光束)という関係を言葉で表現するとややこしいので、先程のHPに乗っているわかり易い図を載せておきます。

ここでちょっと脱線しますが、皆さん電気器具の”消費電力~W(ワット)”っていうのを良くご存知だと思います。これって照明用器具でも同じだって事知ってました?
つまり何が言いたいかって言うと、照明用電球の~Wって言うのは”消費電力”であって、”出力=明るさ”を表していないんです。僕は何の考えも無く、明るさ=W(ワット)数と勘違いしてました。”効率”が関与しますから、言われてみれば当たり前のことなんですよね。(^^ゞ
例えば白熱電球の場合、使用する電気エネルギの90%近くが熱になり残りの10%程度が光になります。従って、60Wの白熱電球が放出する光エネルギーは6W程度となります。そう思うと、6Wって意外に明るいですよね。
白熱電球よりも高効率を謳うハロゲンバルブでは、フィラメント温度が同じであれば寿命を2倍にでき、同一寿命であれば効率が約15%高くなります。ちなみに、ハロゲンランプは、寿命末期に至るまで光束の低下がほとんど無いそうです。比較的安価で輝度も高いため広い応用範囲に使用されています。
そんなこんなで気になるのが”変換効率”です。調べてみると

いや~、正直
がっかり(--〆)です。
”LEDは発熱しなくて高効率”なんて言ってますが、それは”白熱電球に比べれば”であって、蛍光灯のほうが2倍程高いんです。
確かに新しいデバイスですから日々、発光効率は改善されています。しかし、それは他の発光形式の電球でも同じことです。放電灯が総じて高効率で高出力ですが、フィラメントやエミッターの寿命という弱点を持っていました。ところが最近になって無電極放電灯が商品化されました。画期的な長寿命と省電力(高効率)を実現しています。HIDランプに至っても高電圧発生回路がネックでしたが、現在はここまで小型化されています。これらは確かにまだまだ高額ですが、これらの製品のコストダウンが先か、それともLEDの効率改善・大容量化が先かは予断を許しません。発光特性や器具としての特性が異なりますから、競合することなく住み分けられるので要らぬ心配することは無いですかね。(^^ゞ
この辺のネタは、調べれば調べるほど出てくるんですが、脱線はこのくらいで

ようやく長い前フリも終わり、核心のLEDと他のデバイスとの明るさの比較です。
発光体の大きさや、発光特性そのものが違ったり、中には明確な特性表記がされていない物を、なかば強引に比較しますから目安程度にしかならない事をことわって置きます。
光源の明るさを示す単位として最近はルーメン(全光束)がよく用いられますが、白熱電球の場合は40型(36W)で470ルーメン、蛍光ランプの場合では20型(20W)で1150ルーメンぐらいです。これらはデータシートとして公開されています。ランプの規格が同じなら、メーカーが違っても殆んど同じ値です。JIS規格か何かで決まっているのかもしれません。ちなみに手元にある蛍光灯付き懐中電灯は4Wの蛍光管が付いています。昼光色で95ルーメン、白色で110ルーメンあります。6Wの蛍光管だと210~240ルーメンです。
この蛍光灯付き懐中電灯は豆球も付いていますが、残念ながら豆球のデータは公開されていません。
白色LEDの場合は1Wがおよそ38ルーメン、3Wで70ルーメン、5Wで130~160ルーメンぐらいです。それ以下の消費電力のLEDはこちらの表に出ているのを参考にします。
基本的に今はランタンとしての照明性能を探求していますので指向特性の狭いものは除外し、拡散性の強いもので比較してみます。
どんぶり勘定で2~5ルーメン弱というところでしょうか?
【ルーメンとカンデラとの違い】
・光束(ルーメン:lm)を光度(カンデラ:cd)に換算するのは実際には難しいです。カンデラは光を1点の点光源とみなしその点光源から発する光の強さをいうのに対し、ルーメンは360度全立体方向(立体角、ステラジアン:sr)に放射する全体の光の量をあらわす違いがあります。立体角1ステラジアンだけの光の強さを見た場合はルーメン値=カンデラ値となります。cd=lm/sr(カンデラ=ルーメン÷ステラジアン)
指向特性の角度は定格光度の半分50%以上の光度の範囲を表します。(半値角)
・指向特性70度・・光度/光束(カンデラ/ルーメン)cd/lm=0.6、(例)4.8ルーメン=4.8×0.6cd=2.88cd=2880mcd です。
・指向特性30度・・光度/光束(カンデラ/ルーメン)cd/lm=2.0、(例)4.8ルーメン=4.8×2.0cd=9.60cd=9600mcd です。
(光度/光束の定数は各製品によって異なりますので注意してください。) だそうです。(^^ゞ
蛇足ですが、自動車用のHIDの場合、35Wタイプで3000~3200ルーメンです。55Wのハロゲンバルブで1550ルーメン程度だそうです。ハンディーHIDライト(21W)で1000ルーメン・10万カンデラです。
 まさに桁違いですね。
まさに桁違いですね。ハイテクばかりではなく、ローテク=”蝋燭(ろうそく)”も見てみましょう。
そもそも光の明るさを最初に定義する際に基本となったのはどうも”ろうそく”の明るさのようです。candle powerと呼んだそうで、日本に入った際に”燭(しょく)”と訳されました。現在の光の単位になるカンデラ(candela = cd)は燭とほとんど同じ光度を持った明るさで、燭をもとにして正確なカンデラが制定されました。1燭は、1.0067cd(カンデラ)に相当し、今のカンデラが単位として採用されるまでイギリスや日本などで用いられました。日本では1958年(昭和33年)12月31日に「燭」の使用が廃止されたそうです。この辺の経緯は色んなサイトに記述されているので詳しくはそちらを検索してみてください。ですから・・・コールマンさん、ゲニオールさん、ペトロマックスさん
100キャンドルパワーなんて言い方止めて下さい。!

ま、それは置いといて実際の蝋燭(ろうそく)の明かりですが先程紹介した光と光の記録さんに実測したデータが出ています。それによると1カンデラの明かりを出す蝋燭(ろうそく)は(換算値で)炎の体積が337.5立方ミリメートル程度だそうです。はっきり言って想像つきません。

幅10mm、高さ3.3mm程度の炎の大きさの蝋燭ですね。キャンドルランタンはどの程度なんでしょう?誕生日ケーキにともす蝋燭程度でしょうかねえ?先の条件の炎の蝋燭なら1カンデラ、1ルクス、1ルーメンということになります。
さて、マントルを使う燃焼系ランタンはどうでしょう?最近多い表記は~Wと表現しています。W(ワット)ってもともとは仕事率を表す単位です。調べてみると・・・”放射束 (radiant flux)”という概念で表記するようです。
「放射束は、単位時間あたりの放射エネルギーです。これは時間あたりのエネルギーですから、単位は J s-1 ですが、ジュールはワット秒なので、それを代入すると、単位は単にワット(W)になります。ある光源があった場合、そこから単位時間あたりに放射されるエネルギーを表したいような場合には、この放射束を使うことになります。」
なんて書いてあります。光束(ルーメン)とどう違うんでしょう?

”光”は電磁波です。しかし、電磁波が全て光ではありません。人間の可視領域の電磁波だけを”光”と呼びます。人の目に見える電磁波に限った場合、放射束は光束と呼ばれます。これは人間の目の感覚を考慮しているために心理物理量と呼ばれます。したがって、光束は仕事率ではないためにW(ワット)表示されないのです。
このように人間を基準とした測定するための”測光量”とエネルギー放射としての”放射量”を表記する二つの単位系が使われているんです。(そんなことは先に言ってくれよ~
 )
)主な測光量と対応する放射量
主な測光量 単位 主な放射量 単位
光束(Luminous Flux) lm(ルーメン) ・・・・・・・放射束(Radiant Flux) W
光度(Luminous Intensity) cd(カンデラ) ・・放射強度(Radiant Intensity) W/sr
輝度(Luminance) cd/m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・放射輝度(Radiance) W/sr/m2
照度(Illuminance) lx(ルクス)・・・・・・・・・・・・・放射照度(Irradiance) W/m2
厄介なことに僕には簡単には変換できません。1979年:第16回 国際度量衡総会で変換式が決議されたようですが僕にはちんぷんかんぷんです。

電気製品ならともかく、放射量を示すW(ワット)で燃焼系照明器具の性能表示をすることには疑問を感じます。極端な例ですが100Wの能力を持つマントルランタンがあったとします。そのランタンが99%赤外線を放射し、1%光を出した場合でもそのランタンは100Wの能力を持つことになります。これじゃ明るさの比較なんて出来たもんじゃありません。
具体的に見てみましょう。Coleman(コールマン)ノーススター2000ランタンの場合、カタログによると明るさ:約360CP/230W相当となっています・・・相当・・・相当とな?対白熱電球比較でしょうか?ちょっと合わないんですよね

先ず360キャンドルパワーというんですから、光度は約362cd(カンデラ)です。つまり362ルーメンに相当します。白熱電球40型(消費電流36W)で470ルーメンですから、比較するとかなり暗いことになります。輝度が高いので眩しいですが、光量自体は少ないようです。白熱電球の発光効率は10%ですからどんな電球と比較すると230W相当なんて言えるんでしょうね?200Wのシリカ球なら3200ルーメン、自動車の35WのHIDなみの全光束があります。
嘘つき?
まさかね、天下のコールマンがウソなんてつかないですよね。(;一_一)
きっと何か230Wに相当するものがあるんでしょう。照明器具の歴史の中で当初ガス灯(ランプ)が主流でしたが電球の登場と共に廃れて行ったそうです。しかし、マントル発光が発明されて実用になった時再びガス灯が盛り返した時期があったそうです。その当時の電球はまだ発光効率が低かったんですね。きっとその電球と比較してるんだと・・・信じたい。

この一週間、殆んどこれにかかりきりで調べていました。LEDが本当に明るいかどうかを調べるつもりだったんですが、結果は期待外れでした。
5Wなどという特別容量が大きいものは別ですが、通常の超高輝度レベルのLEDが省電力で持ちがいいのは当たり前です。絶対エネルギー量が少ないんです。つまり光量が少ないですから長くも持ちます。それが証拠に3Wクラス以上の製品は一様に大容量の電池を必要とします。
発光効率は蛍光灯の半分~半分強、改善しつつあります。メリットも多く有ります。確かに寿命が長いです。割れることもありませんし、物理的特性もいいです。器具としてもコンパクトになります。指向性の強さもハンディライトとしたら利点になります。蛍光灯などの水銀灯のように温度低下によって発光効率が下がることもありません。
この一週間で得た成果が2つあります。一つは
蛍光灯の素晴らしさです。

物理的特性は劣りますが、発光効率、容量、コストパフォーマンスはずば抜けています。決して大飯喰らいで効率が悪いなんて事はありません。発光量が大きいですから消費が激しく見えるだけです。
2つ目は
これ程光の単位系が、混沌としているとは思いませんでした。

これ程身近にありながら、これ程理解しがたい難解な状態にあるとは思いも因りませんでした。
照明器具の世界に限っては、あまりに生産者側の身勝手が過ぎると思います。消費者に正しい比較が出来るように、きちんと単位系を整えるべきです。
強い行政指導くらい出来ませんかねえ。(--〆)
(あ~疲れた
 )
)Posted by solo380 at 23:18│Comments(3)
│その他
この記事へのコメント
初めまして、本当に、お疲れさまでした。
触れてはいけないところに触れてしまいましたねぇ、明かりは難しいですね
私にはとても真似が出来ません、よく調べましたね。
私の判断基準は、使えるか?使えないか?です。それは、必要な物が
見えるかで判断するようにしてます。
そう言った意味では、LEDのジブカプラスは、「使えます」。真っ暗な場所で
手元が充分見えるし、トイレに行くときの足下も照らせます、何と言っても
あの小ささはLEDの独壇場でしょう。あの白い光は苦手ですが。
その場所でしたいことが出来る明るさ、それが出来る物が「使える物」
じゃないかなぁ、好みとはまた違いますが。失礼いたしました。
触れてはいけないところに触れてしまいましたねぇ、明かりは難しいですね
私にはとても真似が出来ません、よく調べましたね。
私の判断基準は、使えるか?使えないか?です。それは、必要な物が
見えるかで判断するようにしてます。
そう言った意味では、LEDのジブカプラスは、「使えます」。真っ暗な場所で
手元が充分見えるし、トイレに行くときの足下も照らせます、何と言っても
あの小ささはLEDの独壇場でしょう。あの白い光は苦手ですが。
その場所でしたいことが出来る明るさ、それが出来る物が「使える物」
じゃないかなぁ、好みとはまた違いますが。失礼いたしました。
Posted by ライダー at 2006年11月19日 23:52
ライダーさん初めまして、コメントありがとう御座います。
ライダーさんのブログ・・・実は時々拝見しております。m(_ _)m
実際に使用されてコメントされているので、かなりのストックを抱ええておられるんだろうなあ、と勝手に想像しております。
単なる自己満足のために色々調べましたが、結構勉強にはなりました。
しかし、ライダーさんもおっしゃるとおり「実際に使える物」に出会えるかは別次元ですね。僕もヘッドランプでは実用面でPETZL(ペツル)のティカ(旧)で不満は無いんですよ。
「したいことが出来る明るさ」そうなんです、まさにそれを求めているんですよ。僕のモノポールシェルタはちょっと背の高いテント(?)なんで、テーブルと椅子を持ち込んでゆったり読書がしたいんです。重量や体積を無視できればゲニオールあたりが雰囲気もあって低温にも強く、一番なんですがね。
LEDにも電球色が登場しましたので、そのうち「好み」で「使える物」に出会えるかもしれませんね。
またよろしくお願いします。
ライダーさんのブログ・・・実は時々拝見しております。m(_ _)m
実際に使用されてコメントされているので、かなりのストックを抱ええておられるんだろうなあ、と勝手に想像しております。
単なる自己満足のために色々調べましたが、結構勉強にはなりました。
しかし、ライダーさんもおっしゃるとおり「実際に使える物」に出会えるかは別次元ですね。僕もヘッドランプでは実用面でPETZL(ペツル)のティカ(旧)で不満は無いんですよ。
「したいことが出来る明るさ」そうなんです、まさにそれを求めているんですよ。僕のモノポールシェルタはちょっと背の高いテント(?)なんで、テーブルと椅子を持ち込んでゆったり読書がしたいんです。重量や体積を無視できればゲニオールあたりが雰囲気もあって低温にも強く、一番なんですがね。
LEDにも電球色が登場しましたので、そのうち「好み」で「使える物」に出会えるかもしれませんね。
またよろしくお願いします。
Posted by solo380 at 2006年11月20日 23:36
ゲニオールですか、灯油ランタンはオプティマスしか実際に触ったことがないです。あの儀式とも言えるバーナー着火はちょっと良いなと思いますが、毎回だと駄目だろうなぁと思い諦めました。割と面倒なことが嫌いな方なので(^^;).
しかし、あのブラスの何とも言えない雰囲気と音は、静かな林間には似合いそうですね。
しかし、あのブラスの何とも言えない雰囲気と音は、静かな林間には似合いそうですね。
Posted by ライダー at 2006年11月21日 11:18
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。